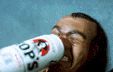
『すこし...』
夕方雨が降ったせいか、星が見えそうなくらい空気が澄んでいる。
公園の角を曲がる時ふと、金木犀の香りに気付いた。
漕ぐ足を緩め、あたりを見回しても、あのオレンジ色は見つからない。
金木犀の香りに初めて気付いたのは中学卒業前の秋だった。
もちろんもっと前からその香りのことは知っていたんだと思う。でも、それまでその香りについて一度も意識したことはなかった。それに突然気付いたのは、その時代好きな人でもいたのか、それとも単にそういう年頃だったからなのか。
あの頃に特別何があったわけじゃなかったように思う。今と変わらない平凡な日々。
私はまた自転車を漕ぎ始めた。
金木犀の香りがだんだん遠ざかっていく。
空を見上げ、少し泣いた...
ということで、この文章はただ「少し泣いた」という言葉を使ってみたくて書いたわけです。
とにかく「少し泣いた」という表現はずるい。
最近唄の歌詞などでもたまに使われている。少し使い古されてきているかもしれない。「泣いた」は別にずるくはない。「少し」というのがずるい。それを説明するのに「少し笑った」という表現でもいい。そこには何か力のない、ふとした幸せな出来事が想像される。
なんだか、それほど裕福でない家庭の母親が、縁側でアルバムを開いては「少し笑った」ような情景が勝手に想像されるではないか。または貧乏な同棲生活で彼女が「幸せよ」と言って少し笑ってもいい。
人に大泣きされたときや大笑いされたとき、びっくりはするけれど、なかなかそこに感情移入できるものではない。
しかし、「少し泣いた」や「少し笑った」という小さな出来事なら、「あっ、わかる...」とわかったような気にさせられるではないか。
日本人の性なのか、「大泣きした」よりも「少し泣いた」ほうが悲しみがこぼれ出すような感情が伝わる。
「アスファルトにサイダーのビー玉のかけらをを見つけた。少し泣いた...」
「渋谷の交差点の人ごみで、昨日まで横にいたコロンの香りに気付き、少し泣いた...」
「空の青さに、少し泣いた...」
もう具体的な出来事なんてなくてもいい、「少し泣いた」で締めくくられれば。
人が「あっ、わかる...」と勝手にわかってくれる。
逆に具体的な表現は避けたほうが「少し」の効力は発揮されるのかもしれない。
そして今日も僕は、小さな悲しみに、少し出会い、少し泣く。